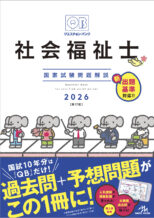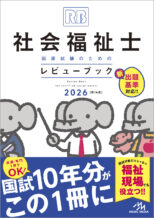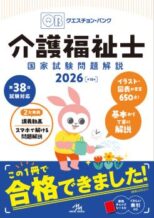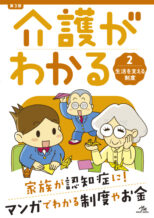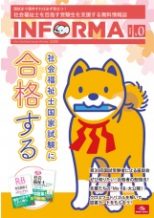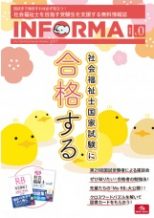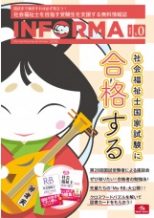福ぞうくんがいく!社会福祉士の活躍
#04 立教大学 コミュニティ福祉学部福祉学科

こんにちは、福ぞうです。
医療、地域、行政、高齢者、障がい、児童、司法…などなど、様々な分野で活躍する社会福祉士たち。
社会福祉士は、利用者さんそれぞれの背景や課題があるなかで、一人ひとりの「その人らしく生きる(wellbeing)」道を一緒に探していきます。
活躍の場がどんどん広がっている社会福祉士に、福ぞうがお話を聞きました。
|
「実務に活きるソーシャルワーク」を伝える社会福祉士
-682x1024.jpeg) 立教大学 コミュニティ福祉学部福祉学科 特別専任教授
立教大学 コミュニティ福祉学部福祉学科 特別専任教授
松山 真 先生
北里大学東病院にて医療ソーシャルワーカーとして、長きにわたり相談支援に携わる。現在は大学で教鞭を執る傍ら、相談援助のプロフェッショナルを対象にした研修をこれまでに500回以上担当。現場経験と教育の両面から、「本当に役立つ相談援助」を伝えることに力を注ぐ。子どもや保護者などが気軽に立ち寄れる新たな居場所「cafe kulübe」のオーナーも務めている。
専門性を発揮できるソーシャルワーカーを育てる
1)全国の研修制度の創立
大学病院の医療ソーシャルワーカーとして活躍されていた松山先生。学校を卒業したばかりの看護師が初勤務日から医療行為に携わることを求められるように、ソーシャルワーカーも同様に専門性を発揮できるようにすべきだと考えていた松山先生は、大学教育に疑問を抱いていたといいます。そこで、ソーシャルワーカーがより実践的な技術を身につけるための全国研修を始めたと振り返ります。
| 看護師は勤務初日でも注射をするのに、ソーシャルワーカーは現場に出てしばらく経験を積まないと、利用者に対する相談援助が1人で行えない状況はよく見受けられます。
若きソーシャルワーカーが面接やアセスメントができるよう、より実践的な指導が必要と考え、相談援助技術を伝える研修をスタートしました。オリジナルのテキストを制作し、3泊4日の研修プログラムを整備して、全国で研修を行ったんです。 |
アセスメント(事前評価)(RB2026 p.520)
支援計画を立案するために利用者の情報を収集し、整理・分析を行いながら問題の全体像を把握する段階。

2)大学教育で実践力を身につけるために
松山先生の実習指導をみた教員から声をかけられ、立教大学に勤めることになった松山先生。大学では従来の座学を中心とした指導ではなく、より実践的な指導を行うことを重視したと語ります。
| 研修や講義の経験から、教育の面白さを感じていたので、大学からの指導依頼を引き受けました。 私が大学に来たときはやっぱり座学が中心で、これではダメだと思いました。そこで、実習教育では記録の書き方など、実際に現場で使う技術を細かく指導しました。実習では現場のソーシャルワーカーが何をしているのかを見て学んでほしいので、疾患の知識や福祉制度等の基礎知識はあらかじめ学習させます。 |
また実習先の開拓・選定も松山先生が自ら行います。優秀なソーシャルワーカーがいる現場で、学生に実践経験を積ませたいという想いがあるそうです。
| 全国研修を通して築いたソーシャルワーカーのつながりを、実習に活用しているんです。 学生に質の高いソーシャルワーク実践をしてもらうために、遠方だとしても優秀なソーシャルワーカーの所に実習に行かせたいと考えています。 |
転換期となった震災の支援活動
1)震災後に感じたソーシャルワーカーとしての使命
東日本大震災がソーシャルワーク活動の転換期だったという松山先生。阪神淡路大震災があった当時、神戸で生活していた経験もあり、いまの自分に何ができるのかを考えたといいます。
| 2011年3月11日、大変な震災が起こりました。こんなことが起きたのに、何もしないわけにいかない、自分の持っている専門性や経験をどうやって活かせるかが問われていると感じました。
阪神淡路大震災の当時、日本医療社会事業協会の社会活動部長として現地視察に向かい、4年間生活していたんです。その経験から震災後どうなっていくのかがなんとなくわかっていたので、復興に十年以上かかるであろう東日本大震災に対して、いま焦って動いても仕方がないということにも気づいていました。それでも学生を連れて早く現地に赴きたいと思い、実現させるにはどうしたらいいか大学と相談を重ねました。半年後、ようやく復興支援活動として活動を開始することができたんです。 |
2)被災地陸前高田での1年間
復興支援活動の準備として陸前高田での活動拠点を探していた際、仮設住宅に移る被災者の方から一軒家を借りることができました。そこに1年間大学を休んで住むことを決めた松山先生。ソーシャルワーカーとしての専門的な仕事と、学生ボランティア活動のサポートに取り組んだと語ります。
| 自分の専門性をどこで活かせるかと考えたとき、市役所職員を助ける間接的援助を行うことを決めました。辛い状況のなか愚痴も言えずに大変な思いをしている職員をサポートすることで、住民にサービスを提供できるような環境を整えたほうがいいと考えたんです。 具体的には、職員のメンタルヘルスケアのためのカウンセリングや、自殺予防対策を行いました。 |
メンタルヘルスケア(RB2026 p.827)
事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置のことである(厚生労働省公示「労働者の心の健康の保持増進のための指針」)。
| また、活動拠点である一軒家に、学生ボランティアと仮設住宅で生活するお年寄りを呼び、夕食会を開きました。
復興支援という名前は当時から使っていません。あくまで目的は陸前高田の人たちと交流すること。一緒に食事することが交流になりますし、それが被災者の心の復興につながります。 |
◆松山先生の今までの復興支援記録はHPにまとめられています。
https://www.maco10.com/
これからもソーシャルワーカーとして生きていく
1)自分でやるしかない、でもそれがおもしろい
自身が学生の頃は今のような未来のイメージはできていなかったと振り返る松山先生。それでもここまで意欲的に取り組んできたモチベーションは「目の前の状況を何とかしなきゃ」という思いだったと続けます。
| 本当は人見知りで人前に出たくないし、しゃべりたくない性格なんです。でも黙っていられないというときがあって、その思いに突き動かされています。
何とかしなきゃいけないけど、全国で誰もやっていない、誰の助けも借りられないから自分でやるしかない。手探りでやるしかなかったけど、それが面白かったんです。 |
 やりたいことを続けていたら、どんどんやりたいことが増えていって今があると松山先生は笑顔を浮かべる
やりたいことを続けていたら、どんどんやりたいことが増えていって今があると松山先生は笑顔を浮かべる
2)最終的に形になるソーシャルワーク
2011年から始まった陸前高田での活動は、現在岩手大学との共同授業へと形を変え、正式な単位として認められるようになりました。また、陸前高田市の高等職業訓練校を活用した「立教大学陸前高田サテライト」を開設し、新しい活動拠点としての形ができつつあります。
このように、ソーシャルワーカーとしての活動を通して組織にまで働きかけるのには、松山先生の強い思いがありました。
| もともとケースワークだけでなく、コミュニティワーク、ソーシャルアクションまで幅広くやるソーシャルワークをやりたいと思っていました。
ソーシャルワークは自分が毎日やっている支援の背景にどんな課題があるのかを把握でき、その要因である社会的な課題にまで取り組むことができる___、最終的には法律や制度のように形になるものなんです。 陸前高田市での活動も、個人的な活動に留めると私が辞めた時点で終わってしまう。システムとして形に残して大学の活動にすれば、人が変わっても誰かが引き継いで継続できる。小さなケースワークでも、最終的にシステムにまで落とし込む必要があるんですね。 |
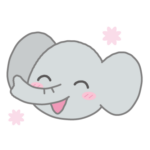
松山先生、貴重なお話をありがとうございました!「ソーシャルワークを最終的に形にする」ことを大切にしてきた松山先生。これからも、伝えること・仕組みをつくることを信念に、ソーシャルワーカーとしての第一線を走り続けてください。

◆現在、松山先生は新たな活動として地域の居場所づくりに取り組んでいます。今後の活動の展望と、ソーシャルワークを担う社会福祉士の在り方について答えていただきました。
→相模原市の親子カフェ KULÜBE 編
▶福ぞうがいく!社会福祉士の活躍シリーズ
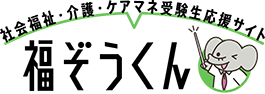





(ドラッグされました)_page-0001-1-154x218.jpg)