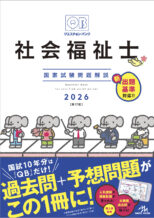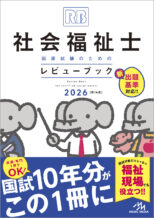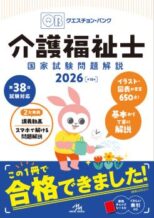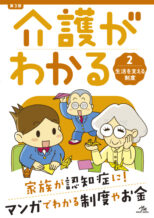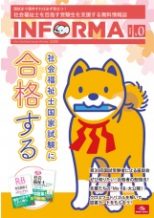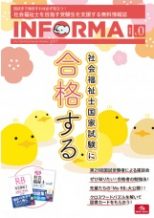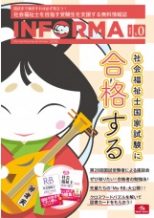福ぞうくんがいく!社会福祉士の活躍
#05 相模原市の親子カフェ KULÜBE

こんにちは、福ぞうです。
医療、地域、行政、高齢者、障がい、児童、司法…などなど、様々な分野で活躍する社会福祉士たち。
社会福祉士は、利用者さんそれぞれの背景や課題があるなかで、一人ひとりの「その人らしく生きる(wellbeing)」道を一緒に探していきます。
活躍の場がどんどん広がっている社会福祉士に、福ぞうがお話を聞きました。
|
前回のインタビュー
福ぞうくんがいく!#04では、松山先生の指導者としての活動や、震災復興に向けたソーシャルワークを紹介しました。松山先生はソーシャルワークが目指す姿として、最終的に法律や制度など形に残るシステムを構築する必要があると考えています。
今回は現在、松山先生が取り組んでいる「親子カフェ KULÜBE」の立ち上げや今後の展望、社会福祉士の在り方について深堀していきます。
住み慣れた地域に「新たな居場所」を作る
ーKULÜBEって?
子どもと親は切っても切れない関係であるように、子どもの支援とお母さんの支援も密接に関係したものです。
地域の中の繋がりが少なくなったと言われ始めてから、長い年月が経つ現代で、どの人が自分を助けてくれるのか分からない人は多くいるのではないでしょうか?
カフェKulübeのオープンが、「仕事として」ではなく「人として」「地域の中で」助け合えるような空気を作っていくことのきっかけになりたいと考えています。
(「KULÜBE 公式HPー私たちについて」より)
1)地域の居場所「KULÜBE」を始めたきっかけ
大学を定年退職後、地域の居場所となるカフェを始めた松山先生。きっかけは35年住む相模原市への地域貢献をしたいという思いからでした。
子ども食堂等のような居場所拠点ではなくカフェという形にしたのは、どんな人でも来やすくするための工夫だと説明します。
| ただ居場所といっても、来るために理由を探さなければいけない場所だと来るハードルが上がってしまうので、飲み物や食べ物があれば気楽な気持ちで立ち寄れるんじゃないかと考えました。
でも、お金が必要だと子どもが来るのは難しいため、ごちそうチケットというお金を出さなくてもいい仕組みを取り入れたんです。 |

いつでも来てねと伝えても、「忙しいだろうから申し訳ない」「自分のことで迷惑かけたくない」と遠慮しがちな子どもたちに、お店に来る言い訳をつくってあげたいという思いから、この仕組みは生まれました。

2)「KULÜBE」に求められる機能
困りごとを相談したり、事が大きくなる前に頼ることができるような、予防的な社会資源が足りないと話す松山先生。KULÜBEはそうした機能を担う場所にしたいと続けます。
| 虐待があったときには児童相談所や警察が対応しますが、保護や措置といった事態になると、家族関係を再構築するのに長い時間がかかります。その手前で何かできることがあるはずだと考えていました。
だけどそういうサービスはお金にもならないし、誰もやろうとしません。サービスによって救える人がいるのであれば、自分でやろうと思いました。 |
松山先生はカフェを運営していくなかで、ただの「居場所づくり」では、本当の地域支援にならないと気づいたそうです。そのためには相談機能を発揮するための具体的な行動が必要だと話します。
ときには親子喧嘩と向き合えない子どもの宿泊場所として、キャパオーバーしそうなお母さんの避難場所としてなど、「KULÜBE」は虐待を防ぐための様々な役割を果たしているようです。
| 2年前にカフェを始めたときは、成人(18歳)し、児童福祉の対象ではなくなる発達障害の子どもたちの居場所づくりを想定していました。
だけど色んな子どもやお母さんと接するなかで、このカフェに求められている機能や役割を考え直すようになったんです。保育士や相談員の経験のあるスタッフや常連の方、学生ボランティア等が協力してくれて、だんだん今の居場所の形になっていきました。 |
 KULÜBEは今年、3階建ての一軒家に移転した。1階はカフェ、2・3階はフリースペースになっている。太陽の光が沢山差し込む明るく優しい空間だ。
KULÜBEは今年、3階建ての一軒家に移転した。1階はカフェ、2・3階はフリースペースになっている。太陽の光が沢山差し込む明るく優しい空間だ。
「KULÜBE」の今後
1)どんな人でも受け入れる相談窓口に
「KULÜBE」は悩みを抱える子どもや保護者に常に寄り添っています。今後のカフェでの展望として、松山先生は「相談機能の強化」を掲げます。
| 国や自治体の相談窓口は法律の縦割りに沿ってできているので、横断するような相談には対応できません。でもここではどんな相談でもいいんです。
自分はソーシャルワークの研究者でありながら医療ソーシャルワーカーとして長年病院で勤務した経験もあるので、制度や疾患の知識も対人援助のスキルもある。ソーシャルワークの専門家として何でもちゃんと答えることができます。このカフェでは日常の相談から高機能相談まで対応できる___どんな人が来ても受け入れる相談窓口にしたいです。 |
2)本当のソーシャルワークができる場所
松山先生は社会福祉士の課題として「福祉も法律の縦割りの一部であること」を指摘します。
| 「福祉」は縦割りの一部なので、組織として総合的に人間を見るということは難しい。
でも「ソーシャルワーク」は本来であれば、人をみて、ミクロ・メゾ・マクロまでちゃんと関わるという総合的な支援ができるはず。ただ、それをできる場所が少ないのが現状です。 だからこそ、ソーシャルワークを理解して実践したいと誰かが志したときに、それができる場所をつくりたいんです。 |
本当の意味でのソーシャルワークを伝えたい、形にできるソーシャルワーカーを育てたいという、松山先生の強い思いを感じた
福祉に関心のあるあなたへ
これから福祉を学んでいくうえで、重要なのは知識ではなく、気持ちだと答えてくれました。どんなに厳しい状況のなかでも自分を突き動かす「価値」を強く持つことが必要だと続けます。
| 「何とかしなくちゃ」という思いが自分のなかに出てくるか___放っておけないと思ったことを、自分がやりたいと思うかどうかですね。
そして「何とかしなきゃ」と思ったときに、方法の1つとして「福祉」があることを知ってほしい。がんじがらめな法制度にやりづらさを感じる場面も多いと思いますが、自由な発想でできる専門職なので、枠組みにとらわれずにやればいいんです。そのために必要なのは、自分がどういう「価値」をもっているかですね。 理想とする支援を追い求めるなかで、「制度上できないから仕方がない」「今までそうしてきたんだから当たり前だ」と理由付けられ、できないと言われる。復興支援の拠点として陸前高田に家を借りようとしたときも、周りからストップをかけられました。ソーシャルワークを形にするためには「信念」を持っていないといけない。動くのをやめたらそこで終わりなんです。 |
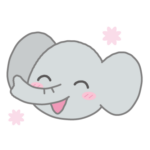
KULÜBEさん、撮影・取材にご協力いただきありがとうございました!取材中も沢山のお客様が来店しており、子ども大人どんな人でも受け入れられるあたたかな地域の居場所として機能していることを感じました。

ここは老若男女いろんな人が集まるカフェです
安心できる居場所がほしい人
誰かに話をきいてほしい人
ちょっとのんびりしたい人
どんな理由でも理由がなくても大丈夫
「コーヒーついで」にお話しませんか?
◆KULÜBEの詳細や営業日についてはHPやInstagramをご確認ください。
HPではごちそうチケットの支援をすることができます。
HPはコチラ
Instagramはコチラ
→https://www.instagram.com/flat_itte_kulube/
親子カフェ KULÜBE
〒252-0234 相模原市中央区共和4-20-6
▶福ぞうがいく!社会福祉士の活躍シリーズ
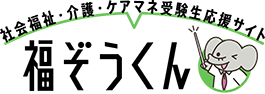







(ドラッグされました)_page-0001-1-154x218.jpg)